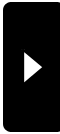スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
理学療法士のできること お気軽にご相談ください
2018年10月21日
地域包括ケア推進リーダー導入研修
2018年10月21日
シルバーリハビリ体操
2018年10月20日

茨城県で大成功している体操です
何のためにどこの筋肉を使って、どうやって動いているか?
その指導士さんを、時間をしっかりとかけて、
解剖・運動学(108項目)まで含み
知的好奇心をきっちりと満足していただけるようにして
自分だけが理解するのではなく
他の高齢者にお伝えすることができるようにする講義もある
受講時の年齢 60歳以上
平均年齢は65〜66歳!
取り掛かりだけ理学療法士等があるものの、後は高齢者がお互いに教える
そのような仕組みになっています。
EーSAS 高齢者のイキイキとした地域生活づくりを支援するアセスメントセット
2018年10月20日
http://jspt.japanpt.or.jp/esas/
E-SAS(イーサス)とは(公社)日本理学療法士協会が、
厚生労働省から平成17年度~19年度に「老人保健事業推進等補助金事業」の4交付を受け、
多くの会員の方のご協力得て開発したアセスメントセットです。
E-SASは介護予防事業「運動器の機能向上」の効果を、
筋力やバランスといった運動機能のみによって評価するのではなく、
参加者(高齢者)が活動的な地域生活の営みを獲得できたか、
という視点から評価することをねらったアセスメントセットです。
言い換えると、参加者(高齢者)が地域で活動的な生活を行っていくために
必要とされる様々な要素を明確にするためのアセスメントセットです。
E-SASにおいて工夫している点は、
「運動機能」に加えて「高齢者のイキイキとした地域生活づくり」を目指した
心理社会的な概念および生活空間に着眼し、実践的ツールとして構成したところです。
「イキイキとした地域生活」が障害の予防や重度化予防のための鍵であることを、

参加者とその家族、介護予防に関わるすべてのスタッフにわかりやすく見せてくれます。
E-SAS(イーサス)とは(公社)日本理学療法士協会が、
厚生労働省から平成17年度~19年度に「老人保健事業推進等補助金事業」の4交付を受け、
多くの会員の方のご協力得て開発したアセスメントセットです。
E-SASは介護予防事業「運動器の機能向上」の効果を、
筋力やバランスといった運動機能のみによって評価するのではなく、
参加者(高齢者)が活動的な地域生活の営みを獲得できたか、
という視点から評価することをねらったアセスメントセットです。
言い換えると、参加者(高齢者)が地域で活動的な生活を行っていくために
必要とされる様々な要素を明確にするためのアセスメントセットです。
E-SASにおいて工夫している点は、
「運動機能」に加えて「高齢者のイキイキとした地域生活づくり」を目指した
心理社会的な概念および生活空間に着眼し、実践的ツールとして構成したところです。
「イキイキとした地域生活」が障害の予防や重度化予防のための鍵であることを、

参加者とその家族、介護予防に関わるすべてのスタッフにわかりやすく見せてくれます。
介護予防推進リーダー研修のご案内 療法士三教会主催
2018年10月20日


本日明日と介護予防に関する
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の教会主催ですが
リハ専門職中心ではありますが
地域でどのように推進を図っていくのかという基本をまとめる
地元のお役に立つにはどうしていくことが良いのか?
それを学んでいく研修です
第2回リハビリミーティングを開催しました
2018年10月19日

岐阜県議会より高殿先生にお越しいただき
県の視野からの医療介護政策についてご説明をいただきました。
高山市からは高年介護課の石腰課長におこしいただき
高山市の介護保健事業・高齢者福祉についてお話をいただきました。
また河野医師にもご参加いただき
症例検討に関し、医師のご意見を賜るという貴重な経験をさせていただきました。
たくさんの療法士・セラピスト・ケアマネージャー・看護師にお集まりいただき
脳卒中片麻痺の在宅リハについてのグループワークを行いました。
顔の見える関係性を作り
「ちょっとこれ頼めんけな?」 という助け合いをするための入り口作りです
スタッフも連絡に、資料の印刷に、駐車場の整備に飛び回ってくれました。
2ケ月に1回程度の開催として、我こそは!というメンバーが集まって進められればと思います。
ご多忙中にお運びいただきましたこと暑く御礼申し上げます
リハビリテーション病院・診療所提供体制ランキング
2018年10月18日

全国のリハビリテーション医療機関(病院・診療所)の
リハビリ提供体制のランキングをみつけました。
レベルではなく療法士の人数ランキングです。
各医療機関の実働人数(常勤換算人数)は各都道府県が公表している医療機能情報サイトで調査し、
リハビリテーション科専門医、理学療法士、作業療法士の合計人数順にランキングしています。
(合計50人以上を掲載)
【情報の出典】 医療介護情報局(http://caremap.jp/)(2014年4月現在)

高山日赤では療法士数合計は 30人(はなさと4含み 岐阜医療情報ポータルより)
久美愛厚生病院では療法士数合計は 21名(院内17+訪問4;HPより)
病床数と療法士数は比例すると思いますが、180人の療法士!
とはすごい数だとおもいます。
愛知医療学院短期大学様にて…
2018年10月18日

愛知医療学院短期大学様にて
学生さん約70名を前に会社説明をさせて頂きました
2日間で50社近くの説明が続きます
学生さん達も史上最高の売手市場
少しでも興味を持ってもらうコツを掴むため
いろんなことを10分間でお話し
実演させていただきました。
脳卒中片麻痺のリハビリが一番興味を持って
頂いた印象でした。やっぱりセラピスト魂が
伝えるべきところかと感じました
たくさんの言葉 神経科学の専門書
2018年10月17日
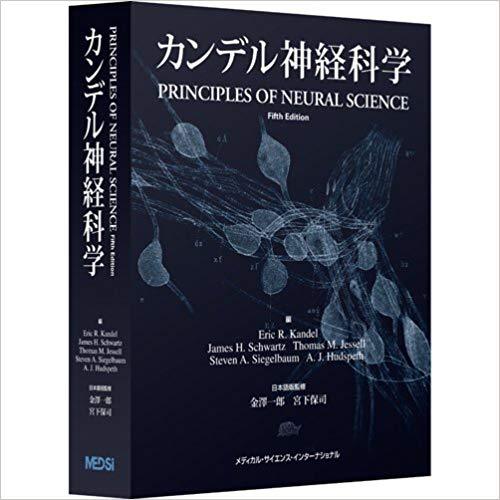
科学的知識は、実験を通じた原著論文から始まると思っています
それが積みあがって専門誌に載り
さらに教科書となるような本書にまとまり
学生さんが簡単に学べるアンチョコ?本となり
一般書に流用され
そして一般知識として広がっていく・・・・
たくさんの基礎用語や分野があります。
これらの分野を広く学び、
お互いに知識を交流し、
広く深い目線で分析する
それがお医者様達だと思います。
お医者様方のわかりやすい言葉の裏には莫大な知識の泉があると思っています。
湧き出る泉の源泉に少しでも近づいて、言葉の裏にある科学を学んでいきたいと思います
目次 全9パート、67章 1649ページ
Ⅰ概論 脳と行動・神経細胞、神経回路と行動、遺伝子と行動
Ⅱ神経細胞の細胞・分子生物学
Ⅲシナプス伝達
Ⅳ認知の神経基板
中枢神経系の構造
知覚と運動の機能的構成
神経細胞から認知へ空間と行動の内的表現
認知機構
前運動野領域の認知機能
認知の機能的イメージング
Ⅴ知覚
感覚の符号化
体性感覚系ー受容器と中枢経路
触覚
痛み
視覚情報の創造的な性質
提示視覚情報処理網膜
中間段階の視覚情報処理と視覚要素
高次視覚情報処理ー認知の影響
視覚情報処理と行動
内耳
聴覚中枢神経系
においと味ー化学感覚
Ⅵ運動
Ⅶ無意識下および意識下の神経情報処理
Ⅷ神経発生と行動の発現
Ⅸ言語・思考・情動・学習
言語
意識的・無意識的心理過程の障害
思考や意欲の障害ー統合失調症
認知機能に影響する自閉症及びその他の神経発達障害
学習と記憶
潜在意識を貯蔵する細胞機構と個性の生物学的基盤
前頭野皮質、海馬と健在記憶の生物学
うーーーんよみきれない・・・・けど眺めています・・・何と莫大な分野!
興味ある分野に集中しつつ、わからないところは連携して考えていく!
この方法でないと・・・いかんとは思っています。